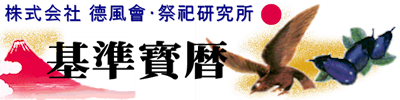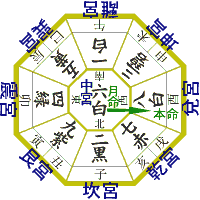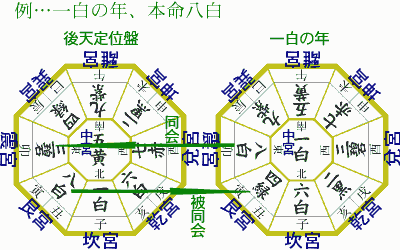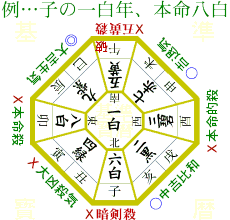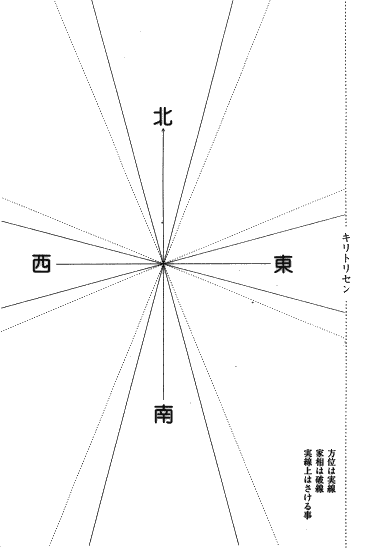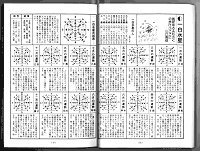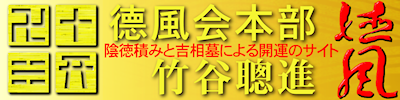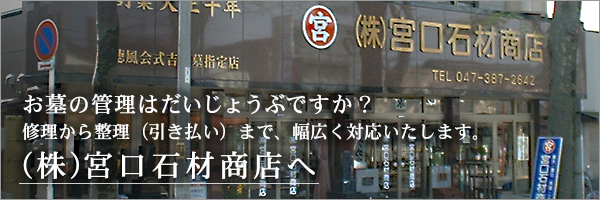●九星の循環
九星は、十二支が12種類の要素を、12年ごと・12カ月ごとに循環するように、9種類の星が9年ごと・9カ月ごとに循環します。
九星の年・月への配置は、陰遁(いんとん)します。陰遁とは逆に繰る事で、八白の次の年は七赤の年と、毎年・毎月数が減っていきます(日への配置は、陰遁と陽遁があり特別な繰り方をする)。
九星の種類
一白水星(いっぱくすいせい)
二黒土星(じこくどせい)
三碧木星(さんぺきもくせい)
四緑木星(しろくもくせい)
五黄土星(ごおうどせい)
六白金星(ろっぱくきんせい)
七赤金星(しちせききんせい)
八白土星(はっぱくどせい)
九紫火星(きゅうしかせい)
●九星盤の見方
九星の後天定位とは、五黄が中心(中宮)の盤で、縦・横・斜めのどれをたしても15になる、魔方陣です。
盤の中心を中宮といい、その年、その月などの九星を表します。
九星は、一定の法則に基づいて毎年・毎月・毎日入れ替わります。(基準宝暦P145をお読みください。)
南が上になり、地図とは逆ですので注意してください。
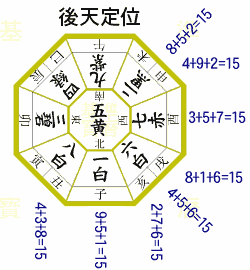
●本命・月命
生まれた年の九星が本命、生まれた月の九星を月命といいます。本命を調べるのには、基準宝暦の見開きや、P162「年号・干支・九星と西暦照合表」をお読みください。 生まれ月の九星は、生まれ年の支より、基準宝暦のP198~P202よりもとめてください。
運命学(九星や四柱推命)では、年の移り変わり目は立春になります。だいたい2月の4日か3日ぐらいです。その前に生まれた方は前年の九星になります。月の変わり目は、二十四節の中の十二節になります。基準宝暦のP166の「節入日表」で大まかな各月の節入り日がわかります。
本命の一部書き出し
一白水星 昭和11・20・29・38・47・56
二黒土星 昭和10・19・28・37・46・55
三碧木星 昭和18・27・36・45・54・63
四緑木星 昭和17・26・35・44・53・62
五黄土星 昭和16・25・34・43・52・61
六白金星 昭和15・24・33・42・51・60
七赤金星 昭和14・23・32・41・50・59
八白土星 昭和13・22・31・40・49・58
九紫火星 昭和12・21・30・39・48・57